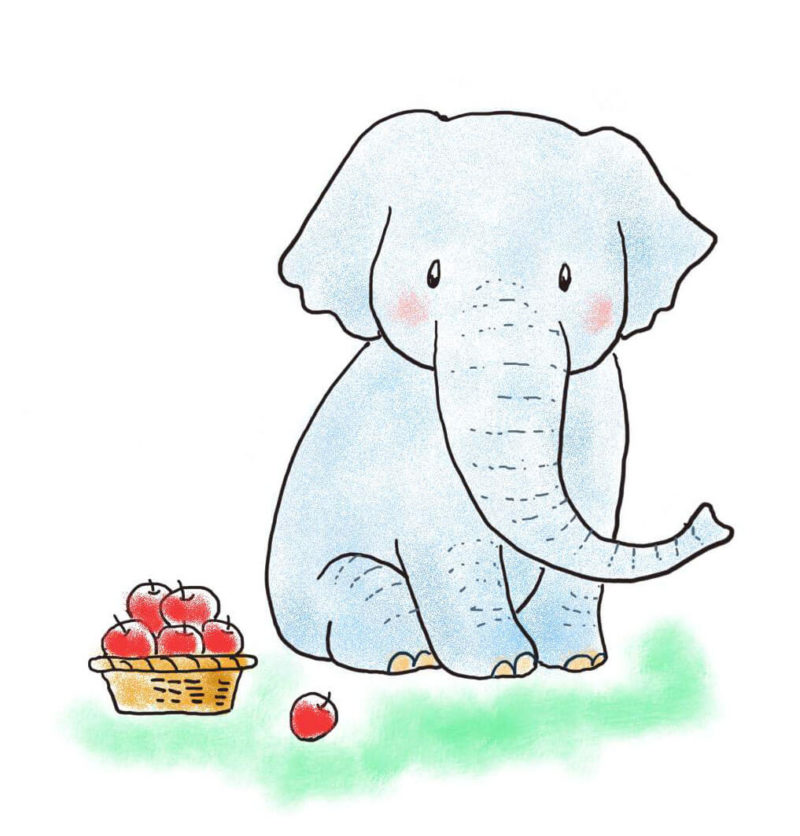
「珍奇男」はエレファントカシマシの3枚目のアルバム「浮世の夢」に収録されております。
このアルバムが出たのが1989年。

だいぶ昔だね。
EPICというレコード会社にいたときです。一番最初に所属してたとこやね。
エレカシだと、よく全然CDが売れなくて契約を切られ、その後「悲しみの果て」で復活→「今宵の月」でブレイク、みたいに言うよね。
だからその全然売れなかったころの曲になります。
「珍奇男」は最初はフォークギターの弾き語りで始まって、なんのジャンル?ていうか、浪曲みたいなとにかく変な歌いだしなんよ。
ていうか、この始まりのとこは、あーちょっと苦手な、好きじゃない感じの曲かなーみたいなるんよね、実は。
でもこの曲はけっこう野心的な造りで、途中からものすごいヘビーなロックになっていくんよ。
宮本さんはかなりこの劇的な構成を狙ってて、それが見事に成功しております。
初めから「珍奇男」という一人称「ワタシ(ワタクシ)」の男が自己紹介するという構成。
「わたくしは珍奇男、通称、珍奇男」
というとこは、どうもつっこみたくなりますが、でもみんな好きなとこなんよ。
歌詞はかなり屈折していて、でも味わい深いです。
実のところ、EPIC時代は名曲が嘘やろ?ってくらい多いのだが。
無意味だけどなんかやっちゃう、この時代で1曲だけにあえてしぼるならどれじゃと勝手に思って、「遁世」かなーと思ったんだけど、「珍奇男」も全く違う世界観でやっぱり凄いんよ、この曲は。

どっちもけっこう長い曲なんだけど、通しで聴いちゃうんだよね。
7分以上もあるんやね。「ボヘミアン・ラプソディ」より長いやん。
また印象だけど、普通の歌手ではあんまり使わないような語彙が多く使われてます。
というのは今書きながら気づいたことで、「寄生虫」という語彙が「遁世」「珍奇男」には共通して出てくるんよ。発見なのか?
「世間の義理に・・・」というところから「ドッ、ドッ、ドッ」とバスドラが参入してきて、サビでハードコアなロックに変わります。(「せけんのきりに」と聴こえるんだよね・・・)
実はけっこうリズムとかルーズなとこがあるんだけど、それがアリな曲なんだよね。
ただ、めちゃめちゃ熱い曲です。ルーズだし、あえてルーズなんだけど、なぜかものすごい緊張感。
「珍奇男」はライブでのパフォーマンスがいつも評価が高い、いわゆるライブで化ける曲ということなんだけど、実はオリジナルのCDの音源も相当なマジックが起こってます。
というか結局このCDの音源がベストなんじゃないかなあ、このときだけの声だしね・・・。
宮本さんはレッド・ツェッペリンが好きなんだけど、この曲はけっこうツェッペリンを感じるんよ。
「フィジカル・グラフィティ」とかあの辺の、緊張感と熱気がある感じ。音楽隊も相当頑張ってます。
エレファントカシマシってプレイスタイルというか、音楽隊が演奏で技術を見せようとしてたのって実はこの初期のころだと思うんよね。
「珍奇男」もただいい曲というだけじゃなくて、メンバー同士の演奏のぶつかり合いの華が見れる曲で。だからライブでも盛り上がるんです。
また「遁世」で思い出したけど、「珍奇男」も宮本さん声そうとう、あのー、シャウトしてるんよ。
これは実は、声が枯れているくらいのこのシャウト、この歌い方によって成立してるところがある。
例えばスティーブン・タイラーとかの、技術としての余裕しゃくしゃくでやるシャウトじゃダメなんよ。
顔をくしゃくしゃにして、汗を流しながら歌うことで、そこまで込みで成立する曲なんだよね。
ということで、今日はエレファントカシマシの隠れた名曲「珍奇男」の紹介でした。
CDで聴くなら、「浮世の夢」が今廃盤で、2万円くらいにまで値が高騰してしまってるので、ベストで入ってるやつの方が手に入れやすいです。
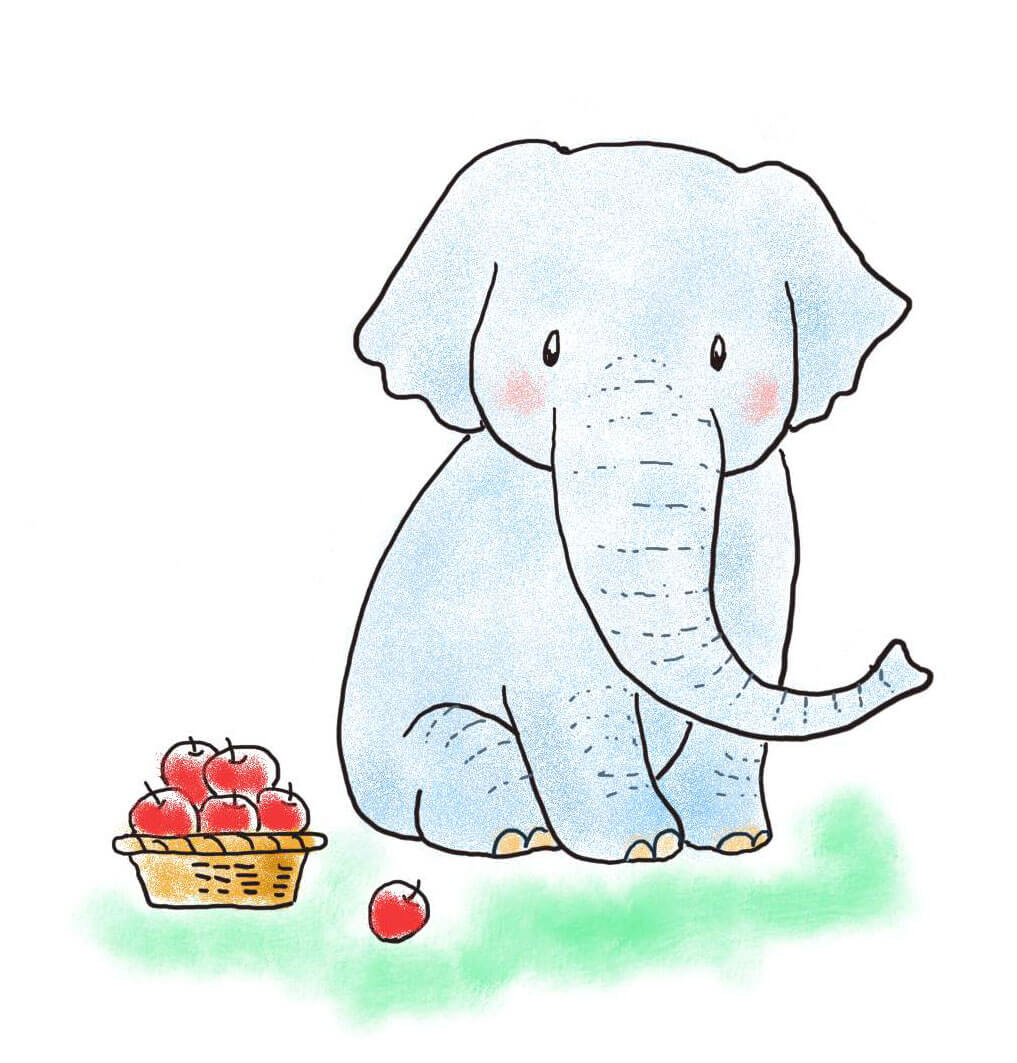

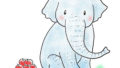
コメント